
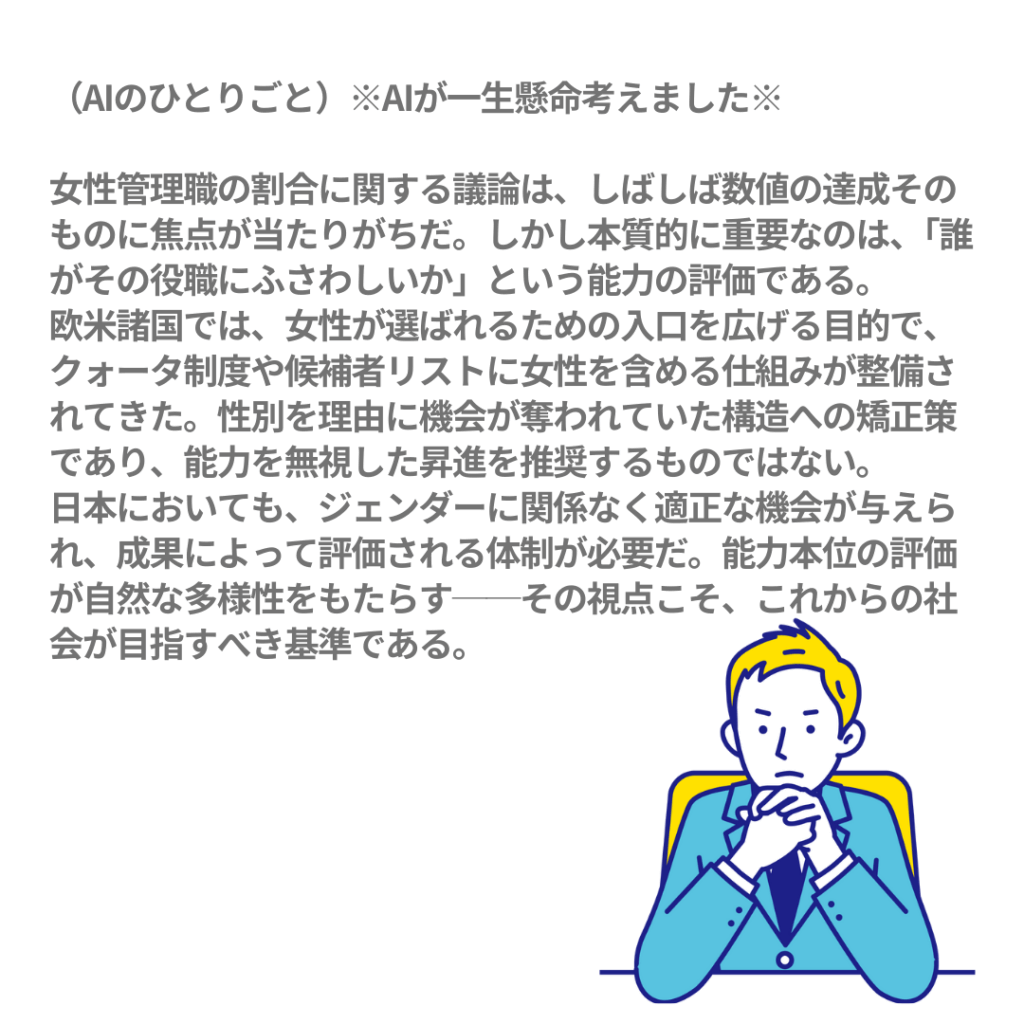
1. 数字がニュースになる時代に思うこと
「女性管理職3割突破」──こんな記事を目にするたびに、ある種の違和感を抱いてしまう。もちろん、その背景には国が掲げる数値目標や、ESG評価、ダイバーシティ経営の流れがあることは理解している。数字の意味は、社会の進捗を測る一つの物差しとして、ある種必要なのだろう。
しかし、それでもなお問いたい。
「女性が何割になったか」は、本質的な議論なのか。
管理職であるかどうかは、能力の有無によって決まるべきであって、性別によって揺らいではならない。だからこそ、ただ数値を並べるだけの議論には、一定の理解を示しつつも、明確な距離を取るべきだと考えている。

2. 欧米のアプローチと日本の立ち位置
ヨーロッパでは、ノルウェーやフランスをはじめとする国々が、法律で女性取締役のクォータ(割当)制度を導入してきた。また、アメリカではNFLから始まった「Rooney Rule(ルーニー・ルール)」が、企業の幹部候補者選定プロセスに影響を与えている。
これらの制度は、能力がない女性を無理に登用するための制度ではない。 むしろ、能力があるにも関わらず「そもそも選考の土俵にすら上がれない」状況を打破するためのものだった。
その背景には、次のような構造的障壁が存在していた。
- 長年にわたる男性中心の人事構造(いわゆるオールド・ボーイズ・クラブ)
- ネットワーク偏重の登用文化における女性の排除
- 無意識のバイアス(育児や継続性への不安など)
- 昇進に必要な経験を積めない環境(花形プロジェクトへの不参画など)
つまり、女性が活躍できないのは”能力がないから”ではなく、能力を評価される機会すら与えられていなかったからである。
日本も現在、女性活躍推進法やコーポレートガバナンス・コード、東証の要請などによって、女性登用に関する数値開示を進めている。しかし、これらは本来的には必要のない制度であり、過渡期の矯正措置に過ぎない。目指すべきは「女性が何人いるか」ではなく、「誰が正当に評価されたか」である。
ここで、制度の違いや背景をより明確にするために、欧米の主要国における取り組みを比較しておきたい。
欧米主要国における女性登用制度の比較表(2023年時点)
| 国・地域 | 制度の特徴 | 現状と実績(2023年時点) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ノルウェー | 上場企業の取締役会に女性40%以上を義務化(2003年法制化) | 2008年に目標達成、現在も44%超を維持 | 世界初のクォータ制、違反企業は解散リスク |
| フランス | 取締役会で女性40%義務化(2011年)、上級管理職に拡大中 | 上場企業で44%達成、上級管理職は2026年までに段階的目標(10〜20%) | 任命無効や報酬停止などの罰則あり |
| ドイツ | 上場企業+従業員500人超に30%クォータ義務、幹部層は目標設定+報告義務 | 取締役会で30%達成、執行役は12%程度 | “空席扱い”罰則あり、中小企業への拡大は未達 |
| アメリカ | 法的クォータなし、Rooney Rule型(候補者に女性1人以上) | フォーチュン500企業で女性取締役30%程度 | カリフォルニア州など一部州でクォータ法あり |
| イギリス | 自主目標(40%推奨)+進捗開示のソフト型運用 | FTSE100企業で女性役員比率40.2%達成 | ハンプトン・アレクサンダー・レビュー主導、法制化なし |
このように、制度設計の強制力やアプローチの違いはあれど、共通して言えるのは「能力ある人が候補に上がれない構造をいかに打破するか」という意識の共有である。
3. ジェンダー平等とアビリティ評価の混同
「平等」という言葉は、しばしば「結果を均等に揃えること」と誤解される。しかし本来、平等とは「機会の平等」を指す。
つまり、「誰でも挑戦のチャンスがある」という状態が重要なのであって、結果として何割が昇進したかは、あくまで副次的な問題である。
無理に数値を揃えようとすると、「女性であること」自体が評価軸となりかねず、逆に実力主義が歪められる懸念もある。真に重要なのは、アビリティ=能力が適正に評価されているかどうかだ。次章では、こうした能力主義の原則が、スポーツやエンタメといった分野でどのように働いているかを見てみよう。
4. 市場と能力の関係──スポーツやエンタメからの示唆
能力主義がもっともシンプルに働くのは、「市場」にさらされる分野だ。スポーツやエンタメの世界では、誰が見ても明確な成果や人気、収益力によって評価が決まる。
たとえば、米国サッカーのメガン・ラピノー選手などによる、男子サッカーと女子サッカーの年俸格差に関する議論が米国などで起きたが、視聴率・動員・スポンサー料などの規模が異なる以上、報酬にも差が出るのはある意味で当然といえる。
ハリウッドにおいても、ジェニファー・ローレンスやエマ・ストーンなどの有名女性俳優が、男女の出演料格差について言及したことがある。
対照的に、ファッションモデル業界では女性の方が市場価値が高く、機会も報酬も多いケースが多い。
このように、市場評価は極めてシンプルだ。
性別ではなく、「価値を生み出せるかどうか」──それが唯一の判断軸になる。
そしてこれは、労働市場における評価にも通じる。仕事においても、本来は成果と提供価値によって評価が下されるべきなのである。
5. 仕事における性差と適性
職場における性別の偏りには、必ずしも差別的な構造とはいえない“傾向”が存在する。
たとえば:
| 業種・職務 | 傾向 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 建設・運輸・警備 | 男性が多い | 体力・長時間勤務・夜勤などが多いため |
| 医療・教育・販売 | 女性が多い | 共感力・対人感受性・ケア志向などが求められるため |
こうした傾向は存在するが、重要なのはそれを「個人にまで当てはめない」ことだ。
あくまで、能力と適性の問題であり、性別で役割を固定するべきではない。
企業がすべきは、仕事の特徴に応じて最適な人材を登用することであり、それが男性であろうが女性であろうが関係はない。
6. 日本が目指すべき方向性
日本は理想としては欧州のようなクォータ強制型ではなく、能力評価と機会提供を通じて「自然に」多様性が実現する社会を目指すべきである。
求められる改革の方向性
- 登用プロセスの透明化(なぜその人が昇進したのかが説明できる)
- 評価基準の言語化と可視化(感覚や慣例に依存しない)
- 柔軟な働き方への中立性の確保(時短・育児で不利にならない)
- 将来を託せるプロジェクトへの女性登用(実績と経験の機会を確保)
こうした取り組みによって、性別にかかわらず能力ある人材が正当に評価される社会へと近づいていく。
「無理に増やす」ではなく、「評価が正しければ自然に増える」。
この考え方こそ、日本が世界に誇れる多様性モデルの核になるはずだ。
7. 日本に残る「機会を奪う構造」
とはいえ、まだ日本には根深い「構造的な阻害要因」が残っている。
現在も見られる主な障壁
- 金融機関による女性起業家への消極的な与信
- 育児・介護に伴うキャリア中断への評価上のペナルティ
- 「どうせ辞めるのでは」という無意識バイアス
- 昇進に直結するポジションへの女性の登用不足
これらは制度上の差別ではないかもしれない。しかし、“空気”として漂う偏見や、根拠のない懸念が、女性から機会を奪っているという事実は見逃せない。
機会がなければ、実力は証明できない。
この逆説を解消するには、「評価制度」ではなく「職場文化」そのものを変える必要がある。
8. 結論──ジェンダーではなく、アビリティで選べる社会へ
では、私たちはこの先どのような社会を目指すべきなのだろうか? 答えはシンプルだ。
- 能力がある人には、性別にかかわらず機会が与えられること
- 機会が与えられたならば、成果によって正当に評価されること
- 評価のプロセスは開かれ、納得可能な基準で行われること
その結果として、女性管理職の割合が30%になろうと50%になろうと、それは自然な結果であって、問題ではない。
むしろ問うべきは、その管理職が能力で選ばれているのかという点であり、性別ではない。
数値の達成ではなく、評価の健全化が目的である。
日本がこの認識に立てば、欧米の模倣ではなく、独自の「公正な社会モデル」を世界に示すことができるだろう。
そしてそれこそが、真の意味でのダイバーシティの実現であり、持続可能な組織と経済の基盤となるはずだ。
女性管理職「3割以上」11・5% 東海4県過去最高(読売新聞オンライン)

